セクションの複数ページをまとめています。 印刷またはPDF形式で保存...
Tips
- 1: 用語解説
- 1.1: IEEE802.15.4とは
- 2: ソフトウェア開発
- 3: ハードウェア開発
- 3.1: 省電力性能について
- 3.1.1: 電池運用とバッファ用コンデンサ
- 3.2: アンテナ実装
- 3.2.1: 逆F型アンテナの実装
- 3.2.2: SMAコネクタの実装
- 3.2.3: ワイヤアンテナの実装
- 3.3: 信頼性のための検討
- 3.4: 特殊ピンの取り扱い
- 3.5: UART-USBケーブルでの書き込み
1 - 用語解説
1.1 - IEEE802.15.4とは
TWELITE-トワイライトはIEEE802.15.4に準拠した無線マイコンモジュールです。
低消費電力と安定した通信性能が特徴です。
特徴
IEEE802.15.4の特徴は以下の通りです。
国際標準規格
IEEE802.15.4とは米国に本部を有するIEEE(アイ・トリプルイー)により策定された標準規格です。標準であることにより1社の独自規格に依存することなく複数のベンダーから規格に基づいた製品が供給されるため安定性を確保できます。2.4GHz帯のISMバンドを使用した場合は日本国内だけでなく世界中で販売可能です。
双方向デジタル通信
IEEE802.15.4は2.4GHz帯の変調方式にOffset Quadrature Phase Shift Keying (O-QPSK)、拡散方式にスペクトラム拡散方式(DSSS)を採用しており妨害ノイズに強く安定したデジタル双方向通信を行えます。
暗号化通信
IEEE802.15.4ではインターネットバンキングやインターネットショッピングにも採用されている強力な暗号化技術128ビットAES暗号によりデータ通信のセキュリティが保たれています。
低消費電力
IEEE802.15.4の設計思想として消費電力を小さくしていることが挙げられます。電池交換なしで年単位の駆動や、コイン電池での駆動、光、熱、振動等から電力を得る環境発電素子(エナジーハーベスター)での駆動が可能です。これにより従来設置が困難であった場所で無線の使用が可能になります。
低速度
IEEE802.15.4は無線LANやBluetoothに比べ通信速度を抑えています。これはワイヤレスセンサーネットワークに最適化した通信速度(250kbps)にすることにより低消費電力と高い通信感度を実現するためです。低速度と表現していますがセンサーネットワークの構築に必要十分な速度を確保しています。
標準プロトコル
IEEE802.15.4は、ZigBeeアライアンスやThread GroupをはじめIETF等の多数の標準化団体によりワイヤレス通信の物理層として採用されています。IEEE802.15.4上で種々の標準通信プロトコルが実装されています。このように通信プロトコルを自由に選択できることもIEEE802.15.4の特徴の一つです。IEEE802.15.4は無線センサーネットワークに柔軟に対応できます。
仕様
| 利用周波数帯 | 2.4GHz | 世界中で使用可能 |
| チャンネル数 | 16 | 16Ch同時通信可能 |
| 変調方式 | Q-PQSK, DSSS | ノイズに強い |
| 伝送速度 | 250kbps | センサーネットワークに最適化 |
| 消費電流(通信時) | <30mA | 低消費電力 |
| 暗号化 | AES-128ビット | 強力なセキュリティを使用可能 |
| ネットワークノード数 | 65535 | 大規模ネットワークに対応 |
IEEE802.15.4 のデータフレーム
以下に IEEE 802.15.4 のデータフレームで規定されたパケット構造を記載します。
| PHYヘッダ(SHR, PHR) | PHYペイロード(PSDU) 最大127バイト | |||||||
| OCTET | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4~20 | n | 2 |
| 内容 | プリアンブルシーケンス | フレームデリミタ開始位置 | フレーム長 | フレームコントロール | シーケンス番号 | アドレス情報 | MACペイロード | FCS |
OCTET(オクテット) はデータ量を表す単位で 1 OCTET = 8bit と定義されています。
現在は一般的ではありませんが1バイト = 8bit でない処理系が存在するため、バイトという単位は曖昧です。通信の定義では 8bit と定義された OCTET が使用されます。
- IEEE802.15.4 MAC API を用いてプログラミングする際、意識する領域は、フレームコントロール・アドレス情報・データとなります。
- シーケンス番号は MAC 層が自動で割り当てるため、ユーザが取得したり値を設定したりすることはできません。
- LQI (Link Qualiry Indicator) 情報はパケット情報には含まれません。パケット受信時の受信回路から得られる情報です。
- 最大パケット長は 127 OCTET (PHYペイロード: PSDU)です。
- 一般的な通信ではアドレス情報が8 OCTETの場合(送信元、送信先ともに16bitショートアドレス)、データ領域(=MACペイロード)は最大 127 - 2(フレームコントロール) - 1(シーケンス番号) - 8(アドレス) - 2(FCS) = 114 OCTET の送信が可能です。
- ZigBee PRO などのスタックでは、スタックが使用するヘッダもあるためユーザが使用出来るデータ領域はより小さくなります。
- 最大パケット時の通信時間は約4.3mSです。
- アドレス情報の構成は以下の組み合わせとなります。
- Src(送信元) の PAN ID (2 OCTET)
- Src(送信元) の アドレス (0: アドレス無し, 2: ショートアドレス, 8: 拡張 アドレス)
- Dst(送信先) の PAN ID (2 OCTET)
- Dst(送信先) の アドレス (0: アドレスなし, 2: ショートアドレス, 8: 拡張アドレス)
- 通常は Src PAN ID, Src ショートアドレス, Dst PAN ID, Dst ショートアドレスの8 OCTETの構成です。
- Src のアドレスだけ MAC アドレスにするような送信も可能です。この場合は、Src PAN ID, Src MACアドレス, Dst PAN ID, Dst ショートアドレスの合計14 OCTETとなります。
| アドレッシングモード | アドレス領域 |
| 送信元、送信先アドレス無し(PAN IDのみ) | 4 |
| 118 | |
| 送信元、送信先16ビットショートアドレス使用 | 8 |
| 114 | |
| 送信元、送信先64ビット拡張アドレス使用 | 20 |
| 102 |
アドレッシングモードは上記以外の組み合わせも可能です。
IEEE802.15.4gとは
IEEE802.15.4gとはスマートメーターの通信を目的とした通信方式の一つです。IEEE802.15.4gで使用できる周波数は国ごとに異なり日本では920MHz帯の物理層(PHY)を用いることができます。MAC層もIEEE802.15.4eで規格化を進めています。両者共にIEEE802.15.4との互換性はありません。日本ではIEEE802.15.4gを主にガスメーターの自動検針を実現するための規格として期待されています。
IEEE802.15.4kとは
IEEE802.15.4kとはスマートグリッドの通信を目的とした通信方式の一つです。IEEE802.15.4kはLow Energy Critical Infrastructure Monitoring (LECIM)と呼ばれており、低速で長距離を確実に通信することを目指しています。
モノをつなぐ無線マイコン TWELITE-トワイライト
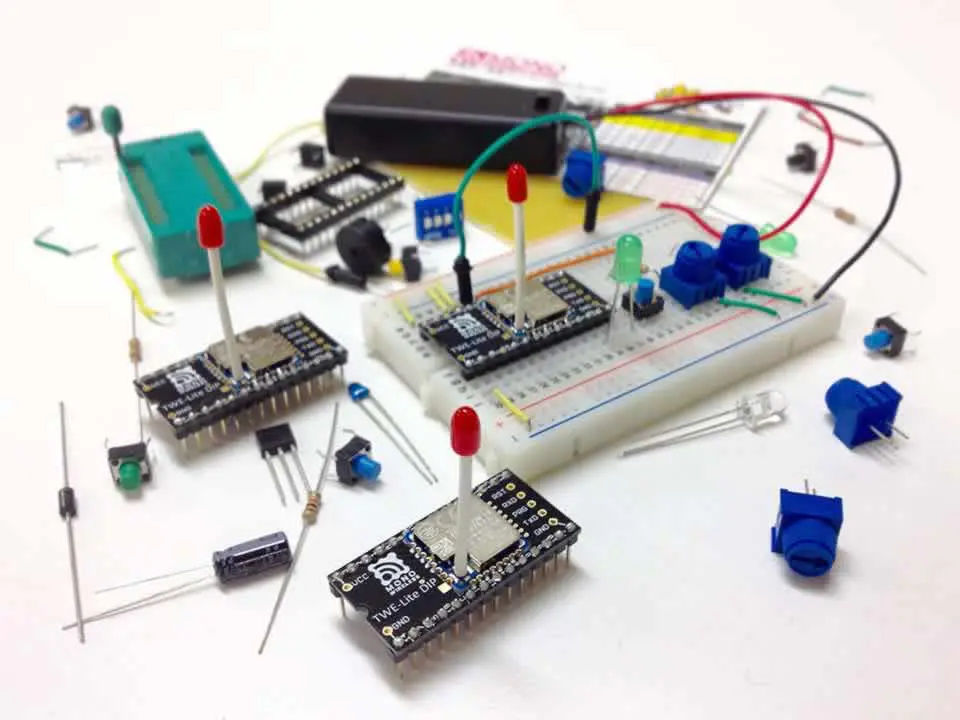
リモコンで何かを操作したいとか何かを監視したいことは日常に数多くあると思います。離れたモノの状態を知りたい場合や離れたモノを操作したい場合には無線が適しています。しかし、モノを無線化する場合には電池寿命、通信距離、同時通信数、大きさ等の様々な制約があり従来の無線では実現が困難でした。 そこでモノをつなぐための無線が誕生しました。
弊社はワイヤレスセンサーネットワークの構築に最適なモノをつなぐIEEE802.15.4に準拠した無線マイコン TWELITE-トワイライトをご提供しており、お客様のワイヤレスセンサーネットワーク関連機器の通信機能開発の簡素化と早期市場投入のお手伝いをいたします。
無線を使って各種センサーの情報を無線で収集するための装置や、各種リモコンを作成したいが、ハードルが高すぎるという方に無線機能を手軽にご使用いただくことを目的としています。TWELITE DIP-トワイライトディップを使用して手軽に無線機能を手に入れることができます。
ホビーや学習用途から各種試作や小ロット量産まで対応し幅広いユーザーにご使用いただけます。
ワイヤレスセンサーネットワークの評価開発(IEEE802.15.4準拠)
弊社では、ワイヤレスセンサーネットワークに応用可能な各種センサー情報を無線でモニターしたり、通信品質測定を行うための開発ツール類もご用意しております。
2 - ソフトウェア開発
2.1 - STAGEアプリを使わずにUART通信する
外部ツールの使用において、当社は一切の責任を負いません。
また、外部ツールに関する質問はご遠慮ください。
TWELITE STAGE アプリが適さない場合
TWELITE STAGE アプリのターミナルは、あくまでも簡易的な評価を目的とした機能です。したがって、シリアル通信アプリの書式モード(アスキー/バイナリ)のように高度なUART通信を行う用途では、次の問題があります。
- TWELITEの
RXへ系列を入力するとき、事前にコピーした文字列をAlt+V/⌘+Vでペーストする必要がある - バイナリデータをHEX(16進数)表記で扱うことができない
CoolTerm の概要
CoolTerm は、シリアル通信に特化した汎用ソフトウェアです。TeraTerm とは異なり、(デバッグモードを使わずとも)バイナリデータを扱うことができるほか、複数のプラットフォームに対応しています。
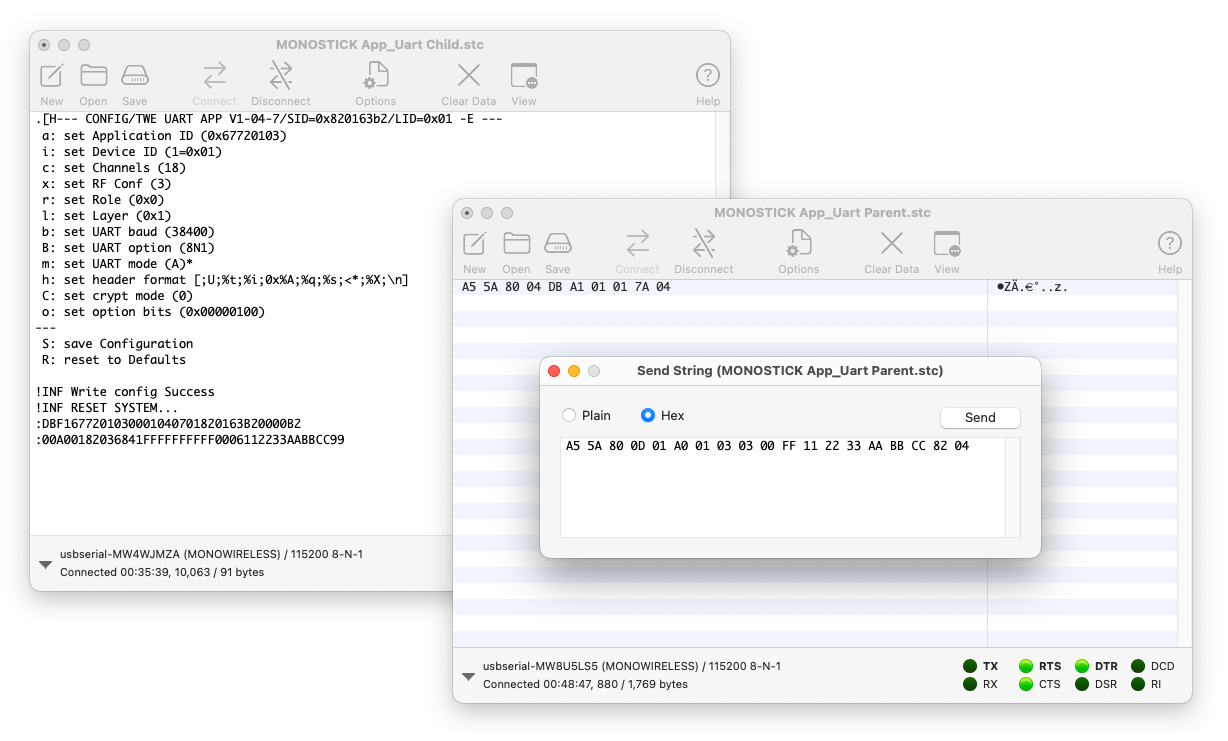
シリアル通信アプリの書式モード(アスキー/バイナリ)を同時に使用する様子
インストール
作者のホームページからファイルを入手してください。
設定
CoolTerm では、使用するシリアルポートと付随する設定に名前を付けることができます。
ここでは、初期状態の TWELITE シリーズへ適合させるために設定が必要となる項目を紹介します。
設定の変更は Options メニューから行います。
Serial Port
Options 中の Serial Port のうち、次の設定を確認します。
Port:使用する TWELITE R あるいは MONOSTICK のポートBaudrate:ボーレートは115200bps
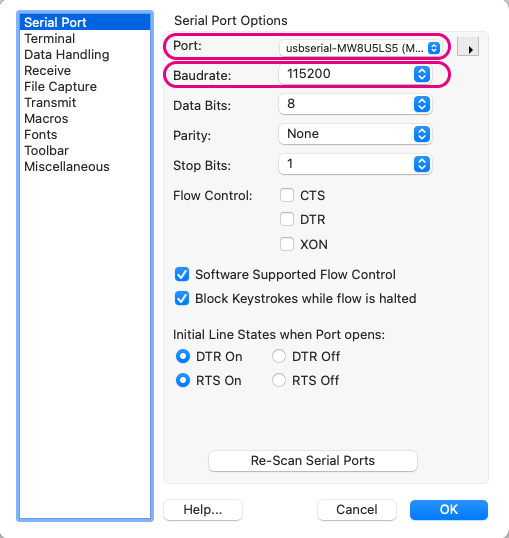
設定例
Terminal
Options 中の Terminal のうち、主に次の設定を確認します。
Terminal Mode:Raw ModeEnter Key Emulation:CR+LF
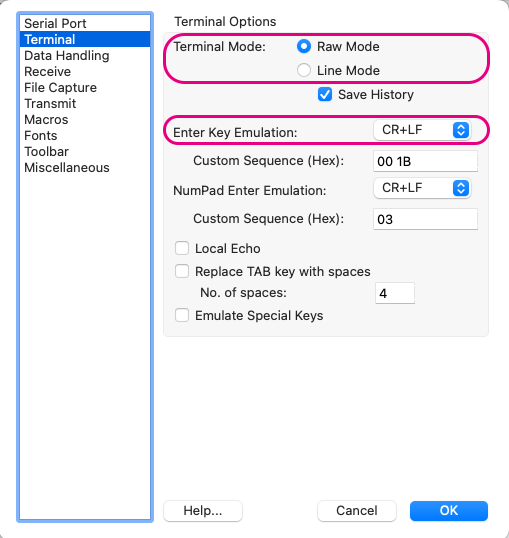
設定例
アスキー形式のデータを入力する場合(インタラクティブモードは除く)は、Terminal Mode を Line Mode としても構いません。
Line Mode では、Enter キーを押すことで打ち込んだデータを一度に送ることができます。
Data Handling
Options 中の Data Handling のうち、主に次の設定を確認します。
Clear Display on:ESC[2J]をチェック(インタラクティブモードの画面消去を有効化)Handle BS and DEL Charactersをチェック(インタラクティブモードの文字消去を有効化)Text Encoding:UTF8
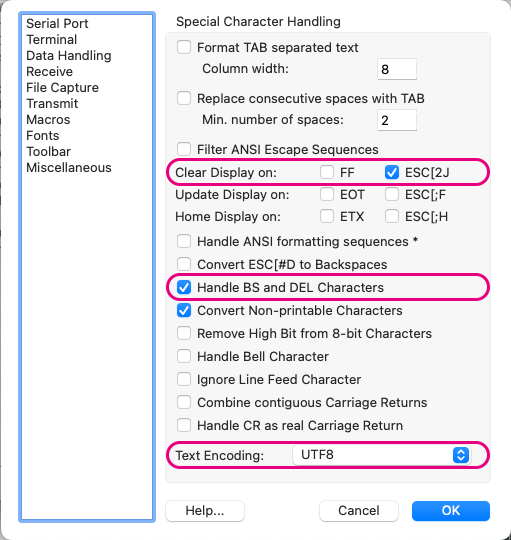
設定例
Transmit
Options 中の Transmit のうち、主に次の設定を確認します。
Send String Options:Terminate 'Send String' DataをチェックTermination String:0D 0A(送信画面ではCRLFを末尾へ追加)
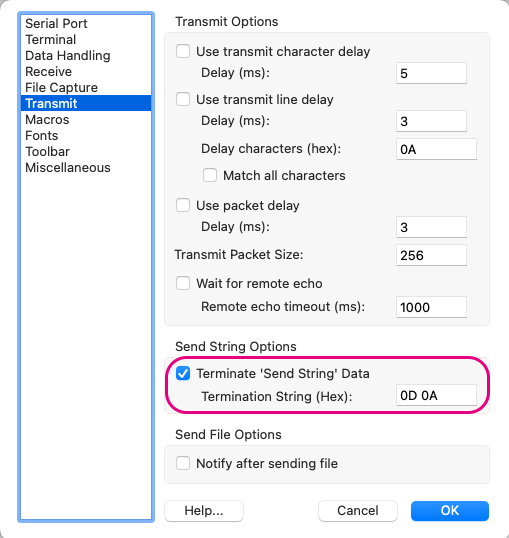
設定例
使用例
インタラクティブモード
インタラクティブモードは、Options > Terminal > Terminal Mode を Raw Mode として使用することを推奨いたします。
Connect をクリックして接続したら、主画面を選択して、+を3回入力します。
TWELITE STAGE アプリと同じように直接文字を打ち込むことで、インタラクティブモードを利用できます。
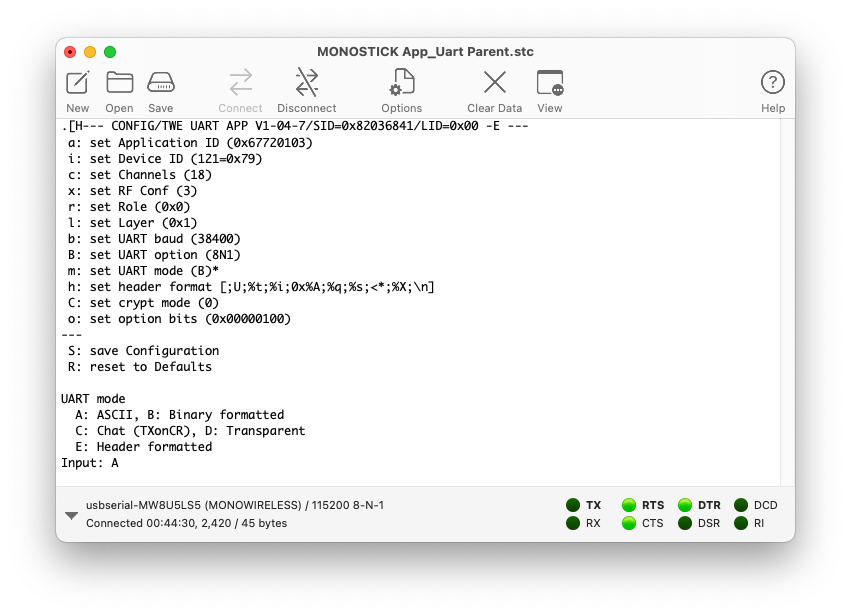
インタラクティブモードの使用例
シリアル通信アプリの書式モード(アスキー)
シリアル通信アプリの書式モード(アスキー形式)のように、:で始まりCRLFで終わるアスキー文字列で構成された系列を扱う際には、Options > Terminal > Terminal Mode を Line Modeとすると便利です。
一行ずつEnterキーを使って入力できるほか、カーソルキーの↑を押すことで履歴を参照できます。
簡易形式を使って、親機から全子機に対してバイト列 0x11 0x22 0x33 0xAA 0xBB 0xCC を数回送信した場合の例を次の図に示します。
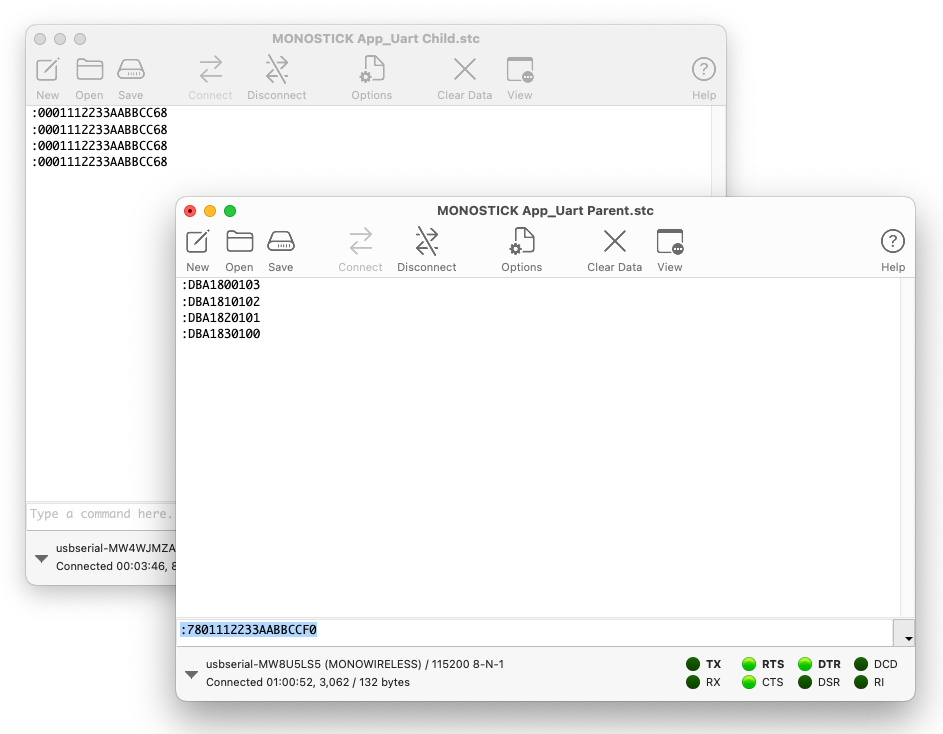
書式モード(アスキー)の使用例
シリアル通信アプリの書式モード(バイナリ)
シリアル通信アプリの書式モード(バイナリ形式)では、Options > Terminal > Terminal Mode を Raw Modeとしたうえで、Options > Transmit > Send String Options > Terminate 'Send String' Data のチェックを外してください。
受信したデータを16進数で表示するためには、View > View Hex を選択します。
16進数で表現したデータを送信するには、Connection > Send String... を選択して送信画面を開き、ラジオボタンのHex を選びます。
簡易形式を使って、親機から全子機に対してバイト列 0x11 0x22 0x33 0xAA 0xBB 0xCC を送信した場合の例を次の図に示します。
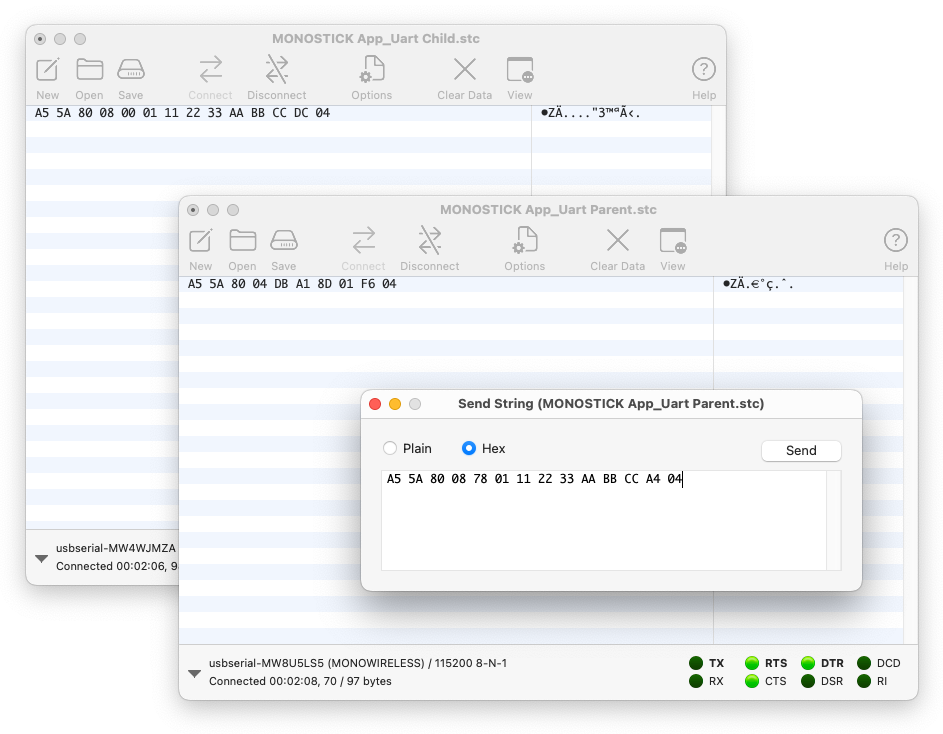
書式モード(バイナリ)の使用例
2.2 - プログラムからインタラクティブモードを使う
インタラクティブモードはシリアルポートを利用するため、機械的に操作することもできます。
生産工程においては、インタラクティブモードを自動的に利用したい場面があるかもしれません。Python を使って設定値を読み書きする例を紹介します。
インタラクティブモードの仕組み
初期状態では、TWELITE の RX ポートは 115200bps 8N1 の設定で動作しています。インタラクティブモードに遷移するには、200msから1000ms程度の間隔で + を3回入力するか、アプリによってはSETピンをLowに落として起動します。インタラクティブモードの操作はASCII文字を入力するだけの処理であることから、自由にプログラムから操作することができます。
実装例
Pythonによるシリアル通信アプリの設定値の読み出し
ここでは、シリアル通信アプリApp_Uartを書き込んだTWELITEから、TWELITE R2/R3 を通じてシリアルIDと設定値を読み出すスクリプトを紹介します。
TWELITE R2/R3 の識別とシリアルポートの取得、また TWELITE R2/R3 によるリセットピンの制御を行うために、tweliter モジュールを利用しています。
pip install tweliter
スクリプト
Python 3.12 を使って実装しています。
シリアル通信アプリの仕様に沿って、ここでは+を3回入力することでインタラクティブモードに遷移させています。
# -*- coding: utf-8 -*-
import time
import re
from tweliter import Tweliter # Mono Wireless module for TWELITE R devices
def get_serial_id_and_settings() -> tuple[str, dict[str, str]] | None:
"""
Get the serial ID and settings from the interactive mode of a TWELITE R device.
Returns:
tuple[str, dict[str, str]] | None:
A tuple containing:
- str: the serial ID (e.g., "0x82010079")
- dict[str, str]: the settings dictionary (e.g., {'a': '0x67720103', ...})
Returns None if the device cannot be accessed or the output is invalid.
Notes:
Example output from the interactive mode of an App_Uart device:
--- CONFIG/TWE UART APP V1-04-6/SID=0x82010079/LID=0x78 -- ---
a: set Application ID (0x67720103)
i: set Device ID (120=0x78)
c: set Channels (18)
x: set RF Conf (3)
r: set Role (0x0)
l: set Layer (0x1)
b: set UART baud (38400)
B: set UART option (8N1)
m: set UART mode (E)
k: set Tx Trigger (sep=0x0d0a, min_bytes=0 dly=0[ms])
h: set header format [;U;%t;%i;0x%A;%q;%s;<*;%X;\n]
C: set crypt mode (0)
o: set option bits (0x00000100)
---
S: save Configuration
R: reset to Defaults
"""
try:
with Tweliter(
type_filter=Tweliter.Type.TWELITE_R2 | Tweliter.Type.TWELITE_R3
) as liter:
# Reset the device
liter.reset_device()
# Get the serial port instance (pyserial)
ser = liter.get_serial_instance()
ser.timeout = 1.0
# Enter to the interactive mode
for _ in range(3):
ser.write("+")
time.sleep(0.3)
# Read the output
raw_output = ser.read_until(b"S:").decode("utf-8")
# Reset the device (Exit interactive mode)
liter.reset_device()
except IOError as e:
print(f"Couldn't open the device {e}")
return None
# Find the settings block in the output
filter_output = re.search(r"---(.*?)---(.*?)---", raw_output, re.DOTALL)
if filter_output:
information_line = filter_output.group(1)
settings_block = filter_output.group(2)
else:
print("No settings block found.")
return None
# Extract serial id from the information line
serial_id_match = re.search(r"SID=0x([0-9A-Fa-f]+)", information_line)
if serial_id_match:
serial_id = f"0x{serial_id_match.group(1)}"
else:
print("Serial ID not found.")
return None
# Extract key-value pairs (str,str) from the settings block
settings_dict = dict(
re.findall(r"^\s*(\w):.*?\(([^()]*)\)", settings_block, re.MULTILINE)
)
return serial_id, settings_dict
def main() -> None:
# Get the serial ID and settings from the device
result = get_serial_id_and_settings()
if result is None:
print("Failed to retrieve serial ID and settings.")
return
serial_id, settings = result
# Show the results
print(f"Serial ID: {serial_id}")
for id, value in settings.items():
match id:
case "a":
print(f"Application ID: {value}")
# case "i":
# print(f"Logical ID: {value}")
# case "c":
# print(f"Channel: {value}")
if __name__ == "__main__":
main()
解説
インタラクティブモードの出力を読み出す流れ
- TWELITE をリセットする
- リセットにより、インタラクティブモードに入るための初期状態に戻します。ここでのリセットは、TWELITE R2/R3 のリセットピン制御によって行います。
- シリアルポートのインスタンスを取得する
pyserialにより、PC 側から TWELITE のシリアル入出力にアクセスするためのインスタンスを取得します。このインスタンスを通じて、後続のコマンド送信やデータの読み出しを実行できます。
+を3回入力する- 一定間隔(200〜1000ms)で
+を3回送信することで、TWELITE はインタラクティブモードに遷移します。この方法はユーザー手動での操作と同様です。
- 一定間隔(200〜1000ms)で
- 保存コマンドの説明
S:まで読み取る- インタラクティブモードでは、設定値が並んだあとに
S:という保存コマンドの説明行が現れるため、そこまで読み取ることで一連の設定内容をすべて取得できます。
- インタラクティブモードでは、設定値が並んだあとに
- TWELITE をリセットする
- 読み出しが終わったら、再度リセットしてインタラクティブモードから通常モードに戻します。
with Tweliter(
type_filter=Tweliter.Type.TWELITE_R2 | Tweliter.Type.TWELITE_R3
) as liter:
# Reset the device
liter.reset_device()
# Get the serial port instance (pyserial)
ser = liter.get_serial_instance()
ser.timeout = 1.0
# Enter to the interactive mode
for _ in range(3):
ser.write("+")
time.sleep(0.3)
# Read the output
raw_output = ser.read_until(b"S:").decode("utf-8")
# Reset the device (Exit interactive mode)
liter.reset_device()
インタラクティブモードの出力を解釈する流れ
一行目と
---に挟まれたブロックを抽出するre.search(r"---(.*?)---(.*?)---", raw_output, re.DOTALL)により、インタラクティブモードの出力から設定全体の情報を2つの部分に分けて取り出します。最初のキャプチャグループは、シリアルIDなどが含まれる情報行(information_line)、2つ目は設定項目が並ぶ設定値ブロック(settings_block)です。re.DOTALLにより、改行を含む全文検索が可能になります。
一行目からシリアルIDを抽出する
re.search(r"SID=0x([0-9A-Fa-f]+)", information_line)を使って、SID=0xに続く16進数のID値(例:82010079)を取得し、それを0x82010079のような文字列に整形します。16進数は大文字小文字を区別せずに抽出されます。
ブロックからコマンドIDと値のペアを抽出する
re.findall(r"^\s*(\w):.*?\(([^()]*)\)", settings_block, re.MULTILINE)を使って、設定値の各行からa: ... (値)のような形式を対象に、コマンドID(1文字)と括弧内の値を取り出します。先頭の空白、コロン以降の任意文字列をスキップし、最初に見つかる括弧内の値のみを抽出します。re.MULTILINEにより、複数行に対応した検索ができます。
# Find the settings block in the output
filter_output = re.search(r"---(.*?)---(.*?)---", raw_output, re.DOTALL)
if filter_output:
information_line = filter_output.group(1)
settings_block = filter_output.group(2)
else:
print("No settings block found.")
return None
# Extract serial id from the information line
serial_id_match = re.search(r"SID=0x([0-9A-Fa-f]+)", information_line)
if serial_id_match:
serial_id = f"0x{serial_id_match.group(1)}"
else:
print("Serial ID not found.")
return None
# Extract key-value pairs (str,str) from the settings block
settings_dict = dict(
re.findall(r"^\s*(\w):.*?\(([^()]*)\)", settings_block, re.MULTILINE)
)
return serial_id, settings_dict
Pythonによるキューアプリの設定値の読み出しと論理デバイスIDの変更
ここでは、キューアプリApp_Cueを書き込んだTWELITEから、TWELITE R2/R3 を通じてシリアルIDと設定値を読み出し、論理デバイスIDを更新するスクリプトを紹介します。
TWELITE R2/R3 の識別とシリアルポートの取得、また TWELITE R2/R3 によるリセットピンの制御を行うために、tweliter モジュールを利用しています。
pip install tweliter
スクリプト
Python 3.12 を使って実装しています。
キューアプリの仕様に沿って、ここではSET ピンを下げることでインタラクティブモードに遷移させています。
超簡単!標準アプリやシリアル通信アプリ等では、SET ピンによる遷移に対応していないことがあります
以下のようにして + を 200-1000ms の間隔で3回入力してください。
def enter_interactive_mode_manually(liter: Tweliter) -> None:
liter.reset_device()
ser = liter.get_serial_instance()
for _ in range(3):
ser.write("+")
time.sleep(0.3)
# -*- coding: utf-8 -*-
import time
import re
from tweliter import Tweliter # Mono Wireless module for TWELITE R devices
def revert_all_setttings(liter: Tweliter) -> None:
"""
Revert all settings
Args:
liter (Tweliter): Tweliter instance
"""
# Get the serial port instance (pyserial)
ser = liter.get_serial_instance()
ser.timeout = 1.0
# Set logical id
ser.write("R")
time.sleep(0.3)
ser.write("S")
def get_serial_id_and_settings(liter: Tweliter) -> tuple[str, dict[str, str]] | None:
"""
Get the serial ID and all settings
Args:
liter (Tweliter): Tweliter instance
Returns:
tuple[str, dict[str, str]] | None:
A tuple containing:
- str: the serial ID (e.g., "82010079")
- dict[str, str]: the settings dictionary (e.g., {'a': '0x67720103', ...})
Returns None if the device cannot be accessed or the output is invalid.
"""
# Get the serial port instance (pyserial)
ser = liter.get_serial_instance()
ser.timeout = 1.0
# Read the output
raw_output = ser.read_until(b"S:").decode("utf-8")
# Find the settings block in the output
filter_output = re.search(r"---(.*?)---(.*?)---", raw_output, re.DOTALL)
if filter_output:
information_line = filter_output.group(1)
settings_block = filter_output.group(2)
else:
print("No settings block found.")
return None
# Extract serial id from the information line
serial_id_match = re.search(r"SID=0x([0-9A-Fa-f]+)", information_line)
if serial_id_match:
serial_id = f"0x{serial_id_match.group(1)}"
else:
print("Serial ID not found.")
return None
# Extract key-value pairs (str,str) from the settings block
settings_dict = dict(
re.findall(r"^\s*(\w):.*?\(([^()]*)\)", settings_block, re.MULTILINE)
)
return serial_id, settings_dict
def set_logical_id(liter: Tweliter, lid: int) -> None:
"""
Set new logical id and save it
Args:
liter (Tweliter): Tweliter instance
lid (int): New logical id
"""
# Get the serial port instance (pyserial)
ser = liter.get_serial_instance()
ser.timeout = 1.0
# Set logical id
ser.write("i")
time.sleep(0.3)
ser.write(f"{lid}\r\n")
time.sleep(0.3)
ser.write("S")
def print_settings(settings: dict[str, str], select: list[str] | None = None) -> None:
"""
Print settings
Args:
settings (dict[str, str]): Settings dict
select (list[str] | None): List of IDs for selected entries. None to select all
"""
for id, value in settings.items():
if select is None or id in select:
match id:
case "a":
print(f"Application ID: {value}")
case "i":
print(f"Logical ID: {value}")
case "c":
print(f"Channel: {value}")
case "x":
print(f"Power / Retry: {value}")
case "b":
print(f"UART Baudrate: {value}")
case "B":
print(f"UART Options: {value}")
case "k":
print(f"Encryption Key: {value}")
case "o":
print(f"Option Bits: {value}")
case "t":
print(f"Transmission Interval: {value}")
case "p":
print(f"Sensor Parameters: {value}")
case _:
print(f"{id}: {value}")
def main() -> None:
"""
Main function
"""
lid_to_set = 25
try:
with Tweliter(
type_filter=Tweliter.Type.TWELITE_R2 | Tweliter.Type.TWELITE_R3
) as liter:
# Revert all settings
print("\nReverting to default settings...")
liter.enter_interactive_mode()
revert_all_setttings(liter)
# Get the serial ID and settings from the device
liter.enter_interactive_mode()
result = get_serial_id_and_settings(liter)
if result is None:
print("Failed to get serial ID and settings.")
return
serial_id, settings = result
print(f"\nCurrent settings for the device {serial_id}:")
print_settings(settings)
# Set logical ID
print(
f"\nModifying Logical ID {settings["i"]} to {lid_to_set}=0x{lid_to_set:02x}..."
)
set_logical_id(liter, lid_to_set)
# Get updated setttings
liter.enter_interactive_mode()
result = get_serial_id_and_settings(liter)
if result is None:
print("Failed to get serial ID and settings.")
return
serial_id, settings = result
print(f"\nUpdated setting(s) for the device {serial_id}:")
print_settings(settings, select=["i"])
# Reset the device (Exit interactive mode)
liter.reset_device()
except IOError as e:
print(f"Couldn't open the device {e}")
return None
if __name__ == "__main__":
main()
スクリプトを実行すると、例えば以下のようにして論理デバイスIDを 25 に書き換えます。
python modify_app_cue_settings.py
Using TWE-Lite-R R27BESFJ @ ftdi://::R27BESFJ/1
Reverting to default settings...
Current settings for the device 0x8201872b:
Application ID: 0x67720102
Logical ID: --
Channel: 18
Power / Retry: 13
UART Baudrate: 38400
UART Options: 8N1
Encryption Key: 0xA5A5A5A5
Option Bits: 0x00000001
Transmission Interval: 5
Sensor Parameters: 0x00000000
Modifying Logical ID -- to 25=0x19...
Updated setting(s) for the device 0x8201872b:
Logical ID: 25=0x19
解説
設定値を読み出す処理
- シリアルポートのインスタンスを取得する
get_serial_instance()により、シリアルポートのインスタンスを取得します。
- 保存コマンドの説明文のある
S:までの文字列をシリアルポートから読み出す- インタラクティブモードでは、設定値が並んだあとに
S:という保存コマンドの説明が表示されます。そこまでの文字列を読み取ることで設定内容をすべて取得できます。
- インタラクティブモードでは、設定値が並んだあとに
- 一行目と
---に挟まれたブロックを抽出するre.search(r"---(.*?)---(.*?)---", raw_output, re.DOTALL)により、インタラクティブモードの出力を2つの部分に分けて取り出します。最初のキャプチャグループは、シリアルIDなどが含まれる情報行(information_line)、次のグループは設定項目が並ぶブロック(settings_block)です。re.DOTALLにより、改行を含む全文検索を行います。
- 一行目からシリアルIDを抽出する
re.search(r"SID=0x([0-9A-Fa-f]+)", information_line)を使って、SID=0xに続く16進数のID値(例:82010079)を取得し、それを0x82010079のような文字列に整形します。16進数は大文字小文字を区別せずに抽出されます。
- ブロックからコマンドIDと値のペアを抽出する
re.findall(r"^\s*(\w):.*?\(([^()]*)\)", settings_block, re.MULTILINE)を使って、設定値の各行からa: ... (値)のような形式を対象に、コマンドID(1文字)と括弧内の値を取り出します。先頭の空白、コロン以降の任意文字列をスキップし、最初に見つかる括弧内の値のみを抽出します。re.MULTILINEにより、複数行に対応した検索を行います。
# Get the serial port instance (pyserial)
ser = liter.get_serial_instance()
ser.timeout = 1.0
# Read the output
raw_output = ser.read_until(b"S:").decode("utf-8")
# Find the settings block in the output
filter_output = re.search(r"---(.*?)---(.*?)---", raw_output, re.DOTALL)
if filter_output:
information_line = filter_output.group(1)
settings_block = filter_output.group(2)
else:
print("No settings block found.")
return None
# Extract serial id from the information line
serial_id_match = re.search(r"SID=0x([0-9A-Fa-f]+)", information_line)
if serial_id_match:
serial_id = f"0x{serial_id_match.group(1)}"
else:
print("Serial ID not found.")
return None
# Extract key-value pairs (str,str) from the settings block
settings_dict = dict(
re.findall(r"^\s*(\w):.*?\(([^()]*)\)", settings_block, re.MULTILINE)
)
return serial_id, settings_dict
3 - ハードウェア開発
3.1 - 省電力性能について
モノをつなぐ無線マイコンモジュールとして低消費電力を実現するためには各処理の消費電流を抑えることが必要ですが、起動時間と処理時間を短縮することも非常に重要です。消費電流が小さくても処理時間が長ければ低消費電力は実現できません。
消費電力(電流)
以下は1パケットを30バイトで送信した時の標準的な消費電流です。
- 標準出力 BLUE-ブルー
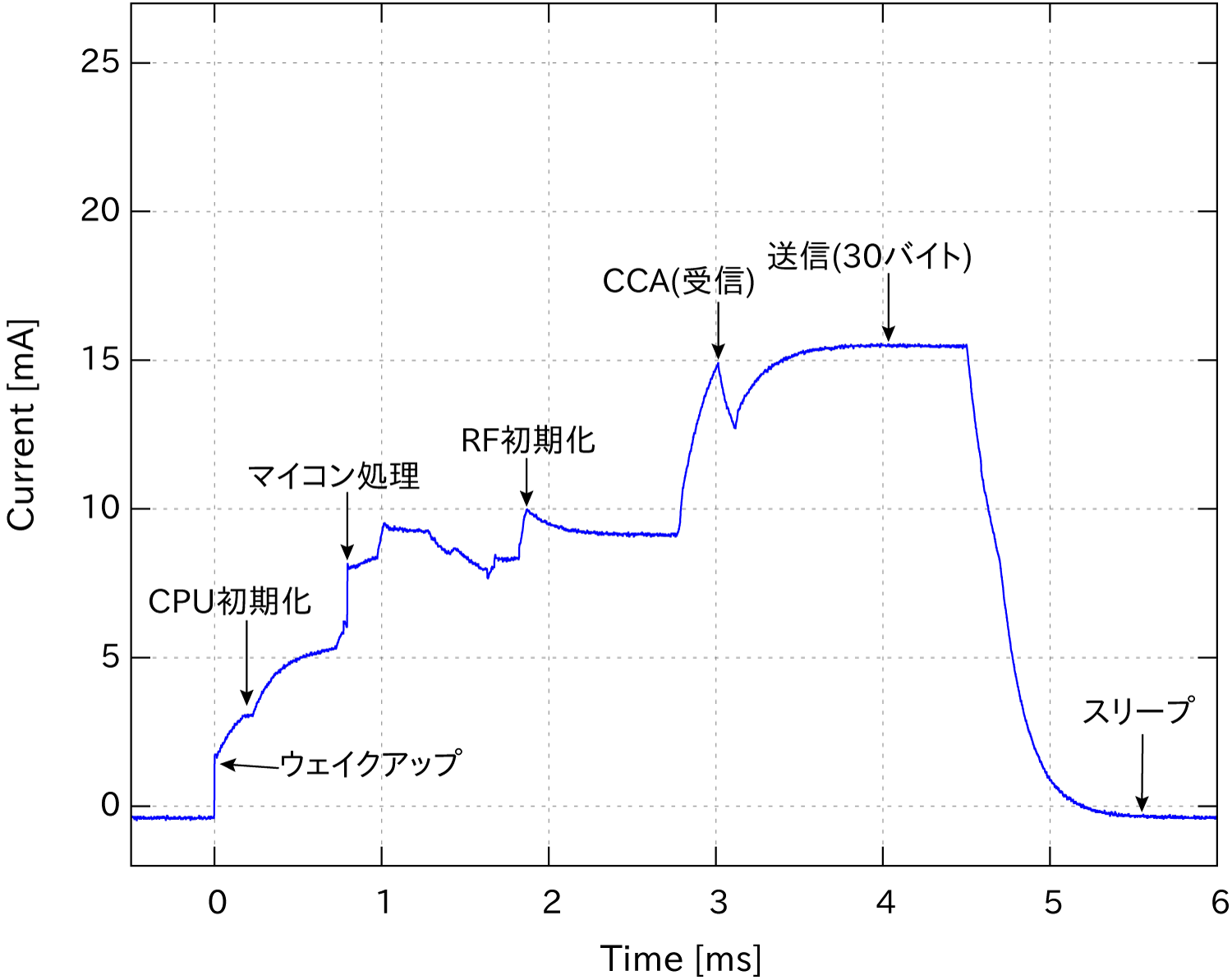
TWELITE BLUEの場合
- 高出力 RED-レッド
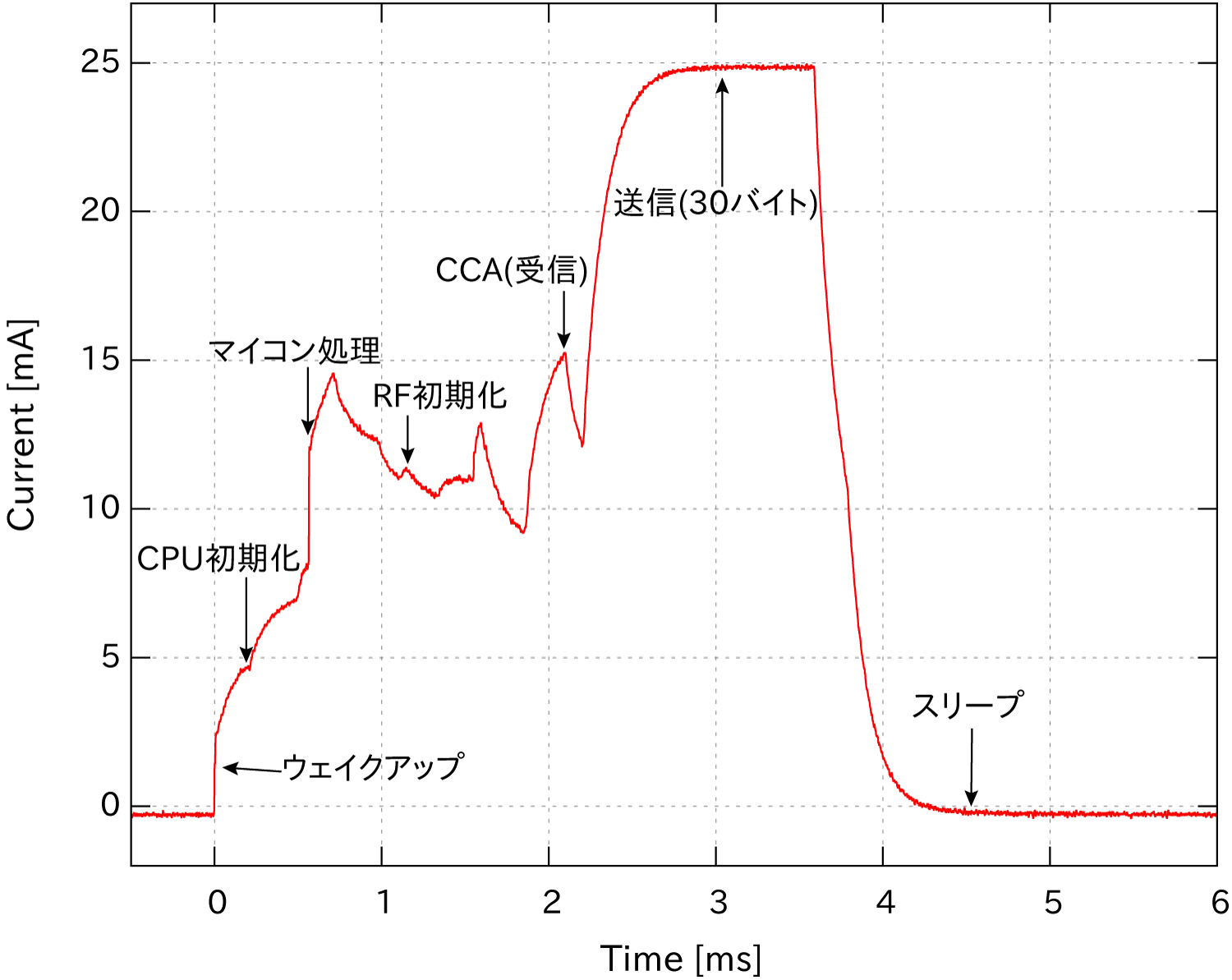
TWELITE REDの場合
高出力 RED-レッドは標準出力 BLUE-ブルーに比べて送信時の消費電流が大きいですが、処理時間が短いので1パケットを送信時の消費電流は同等です。
TWELITE は低消費電流、瞬速起動、高速処理により省電力を実現しています。
17.0mA、RED 14.7mAです。連続受信が必要な場合は常時給電または容量の大きな電池が必要です。消費電力例
TWELITE の消費電力を最小限にした無線タグの例です。この例ではセンサーは使用しておらず、4バイトのIDデータを内蔵タイマーで周期的に送信しています。送信相手からの受信確認(ACK)は行っていません。1パケット送信時の平均消費電流は11.6mA、処理時間は2.5msです。
- 起床中のみ考えた平均消費電流
11.6[mA] * (2.5/1000)[ms] = 29[uA]
- スリープ(RAMオン)時間を含めた平均消費電流
29[uA] + 1.5[uA] = 30.5[uA] = 0.0305[mA]
1秒毎に送信した場合の電池寿命はCR2032の容量を220mAhとして、
220/( 0.0305 ) = 約7213[時間] = 300[日] = 10ヶ月
下のグラフはコイン型電池(CR2032)を使用した場合の電池寿命です。30秒毎にデータを送信した場合の電池寿命は10年を超えます。
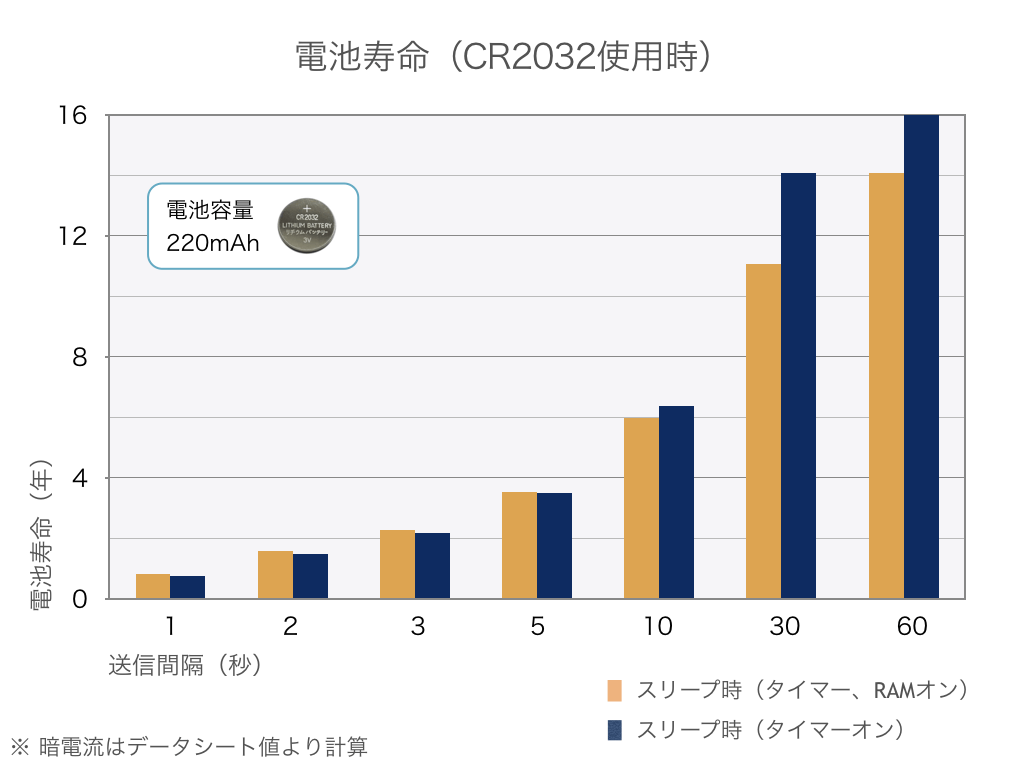
3.1.1 - 電池運用とバッファ用コンデンサ
小容量の電池を使う場合、十分な電流が取れないことがあります。例えば、CR2032 の定格上の電流は 0.2mA 程度で、最大でも 2~3mA 程度しか想定していません。
例えば TWELITEで、無線パケットを送信する場合、瞬間的ですが 20mA 程度消費する事もあり、このとき電流の供給不足、電圧降下などが発生し、システムが正常動作しない事が考えられます。
これを回避するため、バッファ用のコンデンサを VCC-GND 間に接続します。(他にリセットICによる起動制御を行う必要があります)
電源が遮断された場合、電圧3.3V、平均電流が 10mA と仮定して、100uF のバッファーがあれば約10msシステムを動作できます。電源断直後からバッファーからの電流が供給され、無線モジュールが活動不能になる 2V 近傍までは無線モジュールは動作します。
間欠動作・送信時には有効な手段です。注意点として、再送などが発生した場合は送信完了までの時間が大幅に伸びます。1回の再送で数mS消費しますので、再送の回数分を加味したバッファーが必要です。
ただし受信待ちを行うような場合は連続的に大電流 (17.2mA) が消費されることになりますから、上記のようなバッファでの対処は難しく、供給能力の高い電池を利用してください。
コンデンサの容量と動作時間の目安
TWELITEシリーズのモジュールの消費電流は、電源電圧に依存しません。電流一定と言う点から、コンデンサの電荷でどの程度の稼働が見込めるか計算してみます。
静電容量 C のコンデンサに、電圧 v に相当する電荷が蓄積されている場合、一定電流 i で電圧 v から 0 まで降下する時間 t は t = Cv/i となります。
電流 i で 3.3V から 2.1V まで降下するのに必要な時間は、C(3.3-2.1)/i となります。i=10mA, C=100uF とした場合、12ms と計算できます。計算上は 3.3Vで動作していたモジュールの電源が突然断たれた場合、平均電流が 10mA なら 12ms 稼働延長することが期待できることになります。
電流が
10mAというのは、あくまでも平均値の仮定です。実際の消費電流の計測値を参照してください。
3.2 - アンテナ実装
お客様設計の無線回路やアンテナについての認可適用について注意点を記載します。
- 当社により認可を取得し設計情報をお客様に供給する場合
- 当社が提出した認可時の技術情報に従って設計並びに生産を行ってください。
- 当社利用の認可事業者に対してRF回路やアンテナについての技術情報を提出しています。お客様にはこの技術情報に基づいた認可のための必須要件や性能のためのコメントを提示します。
- 認可事業者の見解と異なる見解が存在する可能性があります。万が一、見解の際によって問題が生じた場合は、当社並びに認可事業者は、認可時の技術情報に基づく情報提示を実施しますが、以下については実施しません。
- 当該の交渉を行う、または相当の行為。
- この問題によって生じた補償。
- 海外認可については、お客様自身によって、適合状況をご確認ください。
- 海外認可の要件等は更新されている場合があります。その時点で最新の情報を引用してください。
- お客様の設計・実装について、当社からその是非について最終的な見解を述べることは致しかねます。
- お客様が独自に設計される場合
- ほとんどの場合、独自の設計について認可が必要になります。
- 認可については技術書類等の取り扱いなどをスムーズに行うため原則として当社指定の事業者をご案内します。当社にお問い合わせいただくようお願いいたします。
3.2.1 - 逆F型アンテナの実装
逆F型パターンアンテナ(TWELITE-SMD-ANT-REVF)の電波認証について注記事項を記載します。
リファレンスデザインを下記にて公開しています。
monowireless/PCB_REF_DESIGN_KICAD: Reference Schematic/PCB design data for KiCAD
要件
以下の条件を満足すること。
- 設計データ通りのパターン、スルーホールにより配線すること
- 設計データ中の変更禁止(配線禁止, DO NOT WIRE)領域を変更しないこと
- 指定のプリント基板であること
- プリント基板製造業者へは 1mm 厚を指定してください
- (1mm 以外の基板厚が必要な場合はこちらを参照下さい)
- 誘電率の関係でガラスエポキシ(FR-4)を指定します。他の材料は不可です
- 層構成は両面または4層です
- レジスト色、シルクの指定要件はありません
- 設計通りの製造・実装であることを確認していること
- 一般的に引用される公差を超える設計のずれが無いこと
- 無線モジュールが実装が適切であること
設計と性能
GND面積
逆F型アンテナは、逆F形状のエレメント部と、モジュール直下のGNDパターンから構成されます。GNDパターンの面積が性能に大きく影響します。最適な大きさは 20x20 ~ 40x40mmです。
配線
逆F型は、外部への配線にも影響を受けやい性質があります。例えば、GND面にコイン電池ホルダーを配置し、外部配線無しといった無線タグ (TWELITE CUEなど) は理想に近い性能が得られます。
GND面に一部配線を行う場合は最小限にとどめてください。例えば1本だけ通す程度であれば、ほとんど影響はありません。
性能評価
認可状況
日本国内
対象モジュール
- TWE-L-WX
- MW-R-WX
要件
上記要件を満足すること
北米 (FCC)
※ 海外認可については、お客様自身により適合性について十分ご確認ください。
対象モジュール
- TWE-L-WX
要件
- 上記要件を満足すること
- その他(表示要件)などは FCC の要件を参照すること
欧州 (EU)
※ 海外認可については、お客様自身により適合性について十分ご確認ください。
対象モジュール
- TWE-L-WX
要件
- 上記要件を満足すること
- その他(表示要件)などは CE の要件を参照すること
その他の地域
認可対応無し。
基板厚について
本設計において基板は FR-4 1mm に指定されています。この基板厚は電波認証での認可の根拠であるため、指定外の基板厚の場合、認可外となります。
ただし、日本国内認可に限り以下の基板厚でも認可されています。
- t=0.5mm (当社で取得済みの海外認可での利用は不可)
- t=0.8mm (当社で取得済みの海外認可での利用は不可)
- t=1.6mm (当社で取得済みの海外認可での利用は不可)
アンテナパターンがt=1mmで最適化されているため、僅かながら特性が変化します。ただし変化は多くの場合ごく軽微です。理想GNDサイズに基づく基板上での特性パターンでは 1~3db 程度変化が見られます。
3.2.2 - SMAコネクタの実装
SMAコネクタ(TWELITE-SMD-SMA-CONN)の電波認証について注記事項を記載します。
リファレンスデザインを下記にて公開しています。
monowireless/PCB_REF_DESIGN_KICAD: Reference Schematic/PCB design data for KiCAD
要件
共通
- 設計データ通りのパターン、スルーホールにより配線すること
- 設計データ中の変更禁止(配線禁止, DO NOT WIRE)領域を変更しないこと
- 指定のプリント基板であること
- プリント基板製造業者へは 1mm 厚を指定してください
- 誘電率の関係でガラスエポキシ(FR-4)を指定します。他の材料は不可です
- 層構成は両面または4層です
- レジスト色、シルクの指定要件はありません
- 設計通りの製造・実装であることを確認していること
- 一般的に引用される公差を超える設計のずれが無いこと
- 無線モジュールが実装が適切であること
- 指定コネクタを実装すること
指定コネクタ
トーコネ SMA-LR4(Au)
COSMTEC RESOURCES S-037-TGG
https://akizukidenshi.com/catalog/g/gC-02569/
秋月電子通商取り扱い
認可状況
日本国内
対象モジュール
- TWE-L-WX
- MW-R-WX
要件
- 上記要件を満足すること
北米 (FCC)
認可対応無し。
欧州 (EU)
認可対応無し。
その他の地域
認可対応無し。
3.2.3 - ワイヤアンテナの実装
φ=0.8mm 以下の導線を用いて、アンテナを作成することができます。
任意に折り曲げて使用可能ですが、直立に比べ性能が著しく低下する場合があります。アンテナ性能を維持する場合は「ワイヤアンテナの曲げパターン」をご参照ください。(寸法較差は 0.5mm 未満に収めてください。)